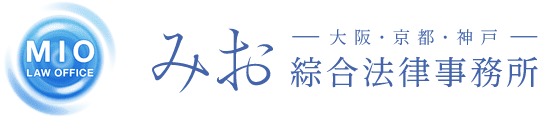破産・倒産する場合の従業員対応

会社・法人の破産について
従業員様にご理解いただくために
社・法人の破産の際、経営者様にとって何よりも心苦しいことは、これまで尽力していただいた従業員の皆様を、予告なく解雇しなければならないことではないでしょうか。会社・法人の破産に伴い従業員の皆様を解雇するときには、私たち弁護士が御社にうかがって、事情をご理解いただくための説明をさせていただきます。以下、どのようにご説明させていただくか、順を追ってご案内します。
-
まずは未払賃金や退職金、
解雇予告手当について
ご説明します従業員の皆様の何よりのご心配は、「明日からの生活」だと思います。「未払の給与はどうなるのか?」「退職金は受け取れるのか?」「突然の解雇の補償はあるのか?」などの疑問に丁寧にお答えすることで、ご心配を少しでも軽減していただくよう心がけています。
-
給与や退職金の支払いについて
最初に、未払の給与や解雇に伴う退職金をお支払いできる見込みがあるかどうかについて、ご説明します。
会社の資金繰りが厳しく、給与や退職金を支払う余裕がない場合には、未払賃金立替払制度を利用して、一部補てんを受けられることをご説明します。
ただし、この制度を利用するには、原則として破産申立て後に破産管財人から証明を受ける必要があるため、この制度を利用してもすぐに給与や退職金をお支払いできるわけではありません。また、この制度では、給与や退職金の全額は補てんされないことになっています。
給与や退職金のお支払がすぐにできない場合は、資金繰りが厳しくやむを得ない状況であることを真摯にご説明した上で、未払賃金立替払制度の説明をさせていただくようにしています。
-
解雇予告手当について
従業員をすぐに解雇するときは、平均賃金×30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、資金繰りが厳しい状況であれば、現実問題として、解雇予告手当をすぐに支払うことはできません。
破産申立てを進めるのであれば、その申立てに必要な費用のほか、少なくとも、解雇予告手当を支払うために必要な資金は確保できるように、資金繰りにある程度余裕があるタイミングを選択することが重要です。
-
ここが重要!(1)
従業員を解雇するには、解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当は、給与・退職金とは異なり、未払賃金立替払制度を利用することができません。やむなく解雇せざるを得ない場合には、何よりも解雇予告手当を優先して支払うことが大切です。
-
ここが重要!(2)
従業員の皆様のご理解をいただくには、給与や退職金、解雇予告手当をきちんとお渡しすることが一番です。「このままでは従業員への給与や退職金が支払えなくなるかもしれない!」と感じたときは、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
-
-
-
雇用保険・社会保険・
税金のことも
丁寧にご説明します従業員の皆様が次に気になるのは、雇用保険・社会保険・税金に関する手続でしょう。これらについても、私たち弁護士が丁寧に説明させていただきます。
-
雇用保険(基本手当)の
制度について解雇によって失業した方は、雇用保険法の特定受給資格者(一般に「会社都合退職」といわれるもの)に該当し、いわゆる自己都合退職よりも雇用保険(基本手当)の受給において有利な扱いを受けます。
特定受給資格者の場合、(年齢や被保険者であった期間によりますが)通常よりも雇用保険(基本手当)の給付を受けられる日数が長くなります。
・特定受給資格者の場合
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 区分 30歳未満 90日 90日 120日 180日 - 30歳以上
35歳未満120日 180日 210日 240日 35歳以上
45歳未満150日 240日 270日 45歳以上
60歳未満180日 240日 270日 330日 60歳以上
65歳未満150日 180日 210日 240日 ・いわゆる自己都合退職の場合
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 区分 全年齢 - 90日 120日 150日 特定受給資格者の場合、いわゆる自己都合退職の場合に課せられる2か月間の給付制限がありませんので、早期に雇用保険(基本手当)の給付を受けることができます。
従業員様を解雇する際、まずは、このような制度についてご説明することが大切です。
また、従業員様が雇用保険(基本手当)の給付を早く受けられるように、ハローワークへの離職証明書の提出を早急に行い、離職票の交付を迅速に受けることが重要です。そのためには、事業停止の準備の弁護士との打合せの中で、離職証明書の作成を早急に進めるについても、検討しておくことが重要です。
-
健康保険の切替について
会社・法人で健康保険に加入していた方は、解雇の翌日に資格を喪失しますので、次のいずれかを選択していただく必要があります。
1. 国民健康保険に加入する
2. 現在加入している健康保険の任意継続を利用する
3. 親族の加入する健康保険の被扶養者になる(扶養に入る)いずれを選択するのが良いかは、各自のご事情によって異なります。従業員様への説明の中では、これらの制度の概要をお伝えしつつ、どの選択がよいかはお一人おひとりの事情によって異なるので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口や協会けんぽ(あるいは健康保険組合)へご相談の上、ご自身に一番合った制度を利用されるようお勧めしています。
従業員様の、各制度への加入手続をスムーズに進めるには、会社・法人の側が、「健康保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構(あるいは健康保険組合)にすぐに提出することが必要です。「健康保険被保険者資格喪失届」が受理されれば、従業員様は、「健康保険資格喪失確認通知書」を年金事務所に発行してもらうことができます。
従業員様が健康保険の切替をお急ぎの場合は、会社・法人の側で「健康保険資格喪失証明書」を発行することもあります。ただし国民健康保険については、会社・法人の側で発行した「健康保険資格喪失証明書」で手続が進められるかどうか、地域によって運用に違いがあるようですので、従業員様に事前にご確認いただくようにお願いしています。
-
住民税の扱いについて
会社・法人の従業員であれば、住民税は通常は給与天引き(特別徴収)の扱いですが、解雇後は、ご自身で毎年支払いをしなければなりません(普通徴収)。こういう取扱いについても、きちんと説明しておくことが大切です。
-
-
経営者様ご自身からも
お話しすることの大切さについて従業員の皆様を解雇する際には、私たち弁護士からの説明だけではなく、経営者様から直接お話しいただくことも必要であると考えています。
法制度のご説明は私たち弁護士がいたしますが、経営者様からお話しいただきたいのは、“これまで会社・法人に尽力してくださった皆様への感謝とねぎらい”です。従業員の皆様にご理解いただくには、私たち弁護士が代弁するのではなく、経営者様ご自身の言葉で、感謝とねぎらいの気持を直接お伝えすることが大切です。

-
私たち弁護士が
全力でサポートいたします事業の停止と解雇の通知の際は、私たち弁護士が従業員説明会に同席し、法制度について、経営者様に代わってご説明します。万が一、従業員様とのトラブルが発生した場合には、ご納得いただくまで丁寧な説明を行います。